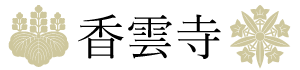葬儀や供養の際に、住職という言葉を耳にする方も多くいらっしゃるでしょう。
どのような方を指す言葉なのか、ご存じでしょうか。
今回の記事では、住職とはどのような方を指すのかについて解説します。
▼住職とは
住職とは僧侶における役職の一つであり、お寺を住まいとして運営や管理を行う人のことです。
仏教に関する知識を持ち、定められた儀式や修行に参加して認められた方が就きます。
また曹洞宗では、方丈(ほうじょう)さんと呼ぶことも多いです。
▼住職の役割
■葬儀や法要での読経
故人の成仏や供養のため、葬儀や法要で読経を行うのも役割の一つです。
お盆やお彼岸・年末年始などに檀家を訪問し、お経をあげる檀家回りを行うこともあります。
■朝夕のお勤め
朝夕のお勤めとして、お寺の本尊への読経を行います。
また、仏飯やお花・お水をお供えをするのも大切なお勤めです。
■仏教の教えを説く
住職は一般の人々に対し、仏教の教えを説いて広める役割があります。
そのため、葬儀や法要で参列者へ仏教の教えを話したり、檀家の相談に乗ったりすることもあります。
■お寺の事務作業や管理
住職はお寺を管理する立場として、さまざまな事務作業を行います。
墓地を持っている場合は、お墓の維持・管理やそれに伴う作業・手続きなども発生するでしょう。
▼まとめ
住職とはお寺を住まいとして運営・管理を行う人のことで、葬儀や法要での読経や朝夕のお勤め・お寺の事務作業や管理などを行います。
また、一般の人々に対して仏教の教えを説くのも大切な役割の一つです。
『宗教法人香雲寺』は佐賀にあり、地域に寄り添うお寺です。
永代供養や納骨堂の運営を通して、故人の霊を大切に供養するお手伝いをしていますので、気になることはなんでもご相談ください。